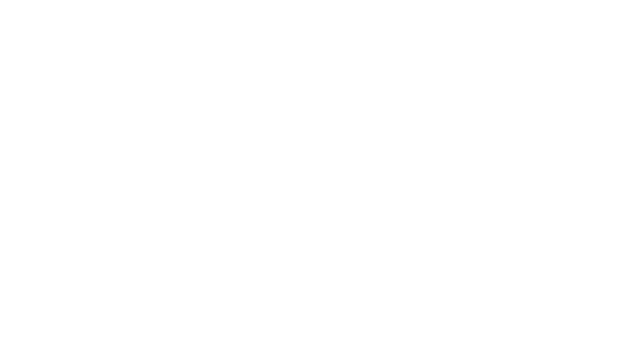
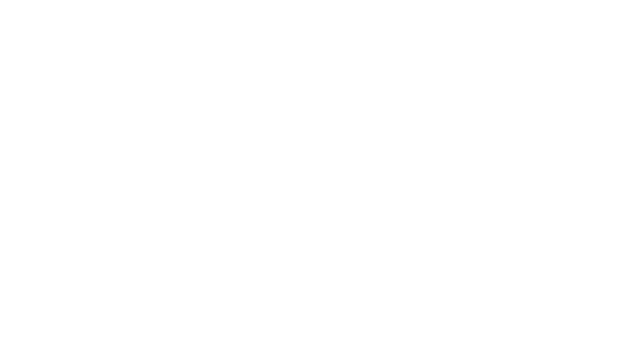
マルティカ・ラミレス・エスコバル監督
インタビュー
幽霊は近くにいる、怖くないし、温かな気持ちになる
PHILBERT DYまずは、あなたとフィリピンのアクション映画との関係から教えてください。
MARTIKA ESCOBARこの映画のアイデアは、モーフェルファンド(フィリピンの映画関連団体)にいた時に生まれました。そのとき演出の先生達もモーフェルファンドを訪れていたのですが、彼らはまるでフィリピンのアクション映画から飛び出してきたような人たちでした。それを見て私は、いつも年配のマッチョな人たちに囲まれている、と思い始めたのです。なぜ、私たちの歴史の中で、何百本もの映画の中で、アクションおばあちゃんは出てこないのだろう、と疑問に思ったのです。
それが種になりました。さらに掘り下げてみると、「フィリピンのアクション映画は細部については具体的に覚えていないにもかかわらず、どんな映画なのかは良くわかるのです。それはなぜだろう」と自問しました。なぜ、こんなにも身近な存在なのだろう。それは、幼い頃から地元のテレビで放映されていた映画に慣れ親しんできたからだと思います。何年もかけて吸収し、自分の中に取り込んでいったのです。
その実感は、書きながらさらに進化していったと思います。アクションというジャンルに、多くの人が影響を受けているように見えるのはなぜでしょう? アクションスターの一人が大統領になるくらいにね。しかも、その一人だけではありません。FPJ(Fernando Poe, Jr、大統領選にも出馬)もいました。そして今も、私たちの政府にはアクション俳優のような大統領、マッチョな人たちがいます。でも、私はそれに共感もしたのです。一人の人間として、スクリーンの向こうの登場人物に救われるかもしれないと、今でもなんとなく感じています。なんだか気持ち悪いですね。そんなの現実じゃないのに。
でもそれは、映画が私たちを変え、人間や人生の見方を変えることができるという証明だとも思います。
重要なのは、TVを正しいと信じ込むのではなく、自分で考えたり、批判したりすることです。私の母は、ティックトックを信じ込んでしまっています。
PD 映画監督として、映画における暴力の描写についてどのように感じていますか?
ME「映画」と「アクション映画」では、かなり違うんでしょうね。「アクション映画」は非常に暴力的でなければなりません。武器も必要だし、血も必要だし、たくさんの人が死ななければならない。しかしそれは、私が取り組む方法ではないのです。この映画では、おばあちゃんというレンズを通して、彼女を取り巻く問題や葛藤を、優しいアプローチで捉えようとしました。愛を通して、コミュニケーションを通して、ね。レオノールはイノセントです、暴力は愛情を持って、立ち向かいます。
私は自分のおばあちゃんに多大な影響を受けています。彼女はとても苦労した人で、いつもポジティブで、笑顔を絶やさない人です。本作を見てもらいました、喜んでいました。
PDええ、それは興味深いですね。私はこの作品を、暴力を問題解決の手段として提示するこのジャンル全体を、国家レベルまで引き上げて清算しているように読みました。ヒーローが暴力で問題を解決するのを見て育った世代から、どのような国が生まれるのかを問うているかのようです。それがあなたの信念ですか? これらの映画と、私たちが今日直面している国家としての問題との間に、関連性を見出すことができると思われますか?
ME直接的な相関関係があるとは言えません。しかし、この国では暴力が普通であるかのように思われるのは、そのせいもあるのでしょう。暴力が物事の解決策になりうるということが常に示唆されているのです。
 PD映画で楽しむ暴力というものはあるのでしょうか?
PD映画で楽しむ暴力というものはあるのでしょうか?
MEそうですね、映画の暴力はドン引きします。でも見返すと、やっぱり面白いんですよ。そうそう、そこが病んでいるところなんです。なぜ、私は暴力を楽しむのだろう? 自分でもよくわからないんです。
PD これらの暴力的なアクション映画を見返して、何を学びましたか?
MEそういう風に考えていなかったので、学んだことは何かと問われると難しいですね。でも、どうしてこんなに似ているんだろうとは思っていました。もし、これらの映画同士を編集してごちゃ混ぜにしたら、どの映画がどの映画なのか識別するのは難しいと思います。アクション映画とは、何か一つの大きな塊のような気がします。
PD お気に入りのアクションスターはいますか?
MEFPJはとても好きでした。彼は最後の最後まで、謙虚でいることをいとわない人でした。彼の描く善良な男にはリアリティがあります。
PD最初のアイデアは、おばあちゃんが主人公のシンプルなアクション映画だと仰ってましたよね。
MEもともとのアイデアは、主人公が自分の人生を終えようとしていて、彼女が書いている映画の中で自分の人生を終えるというものでした。自分の人生がありのままに描かれた人物にこそ、私は最も魅力を感じます。
PDそれのどこに魅力を感じますか?
ME私たちは皆そういうものだと思いますが、私たちの決断はすべて、正しいと思うことに基づいてされます。それが予測できない世界で生きる私たちのあり方なのです。
それは、人間が日々を機能させるためのものだと思うんです。私はそれを書くことだと考えています。そしてそれは、誰かが私たちの人生を書いていると、とらえることができるかもしれません。だから、編集者がいて、監督もいる。自分の人生を書いているのは私たちだけではありません。世界には他の力もあるのです。
PD つまり、あなたは世界をこの共同執筆プロジェクトとして見ているようなものですね?
MEあるいは、私たちは自分の人生を書いているとばかり思っていて、本当は他の誰かが書いている、などですかね。
PD それは、宗教的なものですか? それより高い力ですか?
MEむしろ、なぜ私はこのようなことをしているのだろう? なぜ、このようなことが起きているのか? なぜ映画を見たいと思う人がいるのか? 誰のための映画なのか? 何のためなのか? ということをいつも考えているんです。でも、この世界には独自の決定論があるような気がします。私たちは自分の人生を書きたいと願っても、それはできません。
PDあなたの映画には幽霊が登場します。どの時点で、幽霊と会話できる世界にしようと決断したのでしょうか?
MEそうですね、私は本当に幽霊と話ができるような気がしているんです。私たちが必要とするとき、彼らはそこにいるのです。私は霊を信じますし、人に思いを伝えることができると信じています。そして、幽霊が私たちに反応することを信じています。夢や思考を通してね。
映画に出てくる幽霊は、私の家族の話からきています。私の母と祖母は、25歳で亡くなった叔父の話をしてくれました。その叔父が、幽霊になって、ベッドで二人の横に座っていたことがあって、それが、私にとって、幽霊の存在という考え方の原点となったイメージです。私たちは、幽霊と共に生きています。彼らはここにいるが、私たちは彼らの体を見ることができないだけなのです。
PDそれは特にアジア的なものですよね。西洋の伝統では、幽霊を見たらパニックになりますよね。でも、アジアでは、私たちは幽霊の中で暮らしています。映画の中で、幽霊は単に彼らの生活の一部である、と表現していますね。それは、あなたの考え方なのでしょうか?
MEそうですね。
フィリピンでは死者が近くにいると信じられています。アピチャッポン監督「ブンミおじさんの森」でもそうです。
PD幽霊に関する個人的な体験はありますか?
MEいいえ。でも、信号が送られてきたら信じますね。
PDどのような信号ですか?
MEこの映画を完成させたとき、祖父が亡くなりました。そして、この映画がいつかどこかで大勢の観客を集めて上映されるようにと願ったんです。祖父は、私にサンダンスを与えてくれたような気がします。彼は、私が望むものを知ってくれていたのです。私が望むもの、つまり大勢の観客です。
招待状をもらったとき、真っ先に感謝したのは祖父でした。でも、これは私の言い訳で、世の中をそういうふうに理解しようとしているだけかもしれません。私たちは皆、この人生に意味があるように見いだし、パターンを見つけようとしているだけなのです。
PDこの映画には、とても個人的な側面があります。文字通り、あなた自身がこの映画の中に入っているのです。この映画を作るにあたって、どのような場面でそれが生まれたのでしょうか?
MEそれは脚本にありましたね。たぶん2、3稿目。この映画は、私が人生で何をしたいのかに向き合うことでもあるような気がします。つまり、8年前なら、それは映画製作だったと言えるでしょう。でも、今はそうでもない? わからないですね。
PDでは、どのようにしてそこにたどり着いたのでしょうか? 映画の中で自分が映画の終わり方について話すことになったのはどうしてですか?
MEそうですね、深夜で、眠れなくて、これが私のために書かれた人生なのかなって思ってて……そうでないような気がしたからです。編集者がいるような、違う星があるような、誰かがコントロールしているような、そんな気がしたんです。そこで、編集を見るというシーンを出したんです。
PD本作はかなり長い間、制作が続けられてきました。最初に思い描いていたものと、最終的な作品はどれくらい違うのでしょうか?
 MEかなり近いと思います。撮影を始める頃には、自分が何を目指しているのかは、はっきりしていました。最初の4年間は、この作品の撮影で、ストーリーの本質を見極めるために多くの時間を費やしました。まだ若い映画監督だった私は、この映画にたくさんのアイデアや独創性を盛り込もうとしていました。それがだんだん削られていき、より共感性のある、あるいはより意味のある決断ができるようになりました。この映画は、私と共に歳をとっていったのです。脚本は25稿に及びました。
MEかなり近いと思います。撮影を始める頃には、自分が何を目指しているのかは、はっきりしていました。最初の4年間は、この作品の撮影で、ストーリーの本質を見極めるために多くの時間を費やしました。まだ若い映画監督だった私は、この映画にたくさんのアイデアや独創性を盛り込もうとしていました。それがだんだん削られていき、より共感性のある、あるいはより意味のある決断ができるようになりました。この映画は、私と共に歳をとっていったのです。脚本は25稿に及びました。
PD本作を制作する上で、一番苦労したことは何ですか?
ME明らかに資金調達ですね。撮影の8年間は、物乞いの8年間でもありました。カメラオペレーターやTVCMなど様々なアルバイトをしました、クッキー販売も。女性だけで「ワンウーマンチーム」を作り、仕事を紹介したり、お互いを支えあったりもしています。フィリピンではあらゆる高位のポジションは男性が占めていて、ジェンダーギャップ指数ではアジア一位ですが・・・まったくそうは思えません。女性監督は男性の2倍働かないと認めてもらえません。
撮影は22日間、製作費は15万ドル、低予算映画なので、友達にエキストラを頼むなど苦労しましたが、楽しかったです。母はテレビ撮影セットの停電シーンに、祖母は病院でのダンスシーンにエキストラで出演しています。
他に大変だったのは、この映画の正しいエンディングを見つけることだったと思います。エンディングのバージョンは4種類ありました。(プロデューサーの)MarioとMonsterがエンディングを見たとき、「物語はどこにあるのか? アークはどうなったんだ? 母子の物語はどうなったんだ?」と聞いてきました。それらを見つけるのに、彼らは本当に大きな助けになってくれました。
PDこの映画は、少なくとも部分的には、この映画監督が、自分の作品によって社会全体に対して何を働きかけてきたかを理解する内容にもなっています。
MEはい。私には映画監督としての責任があると思います。そして私が発信したものを人々が受け入れてくれるということを確信しています。
PD映画監督としての責任は何だと思いますか?
ME私はただ、人々に何か良い貢献をしたいのです。人生をもっと愛おしく思ってもらえるように。それがいつも私の原動力です。
世界を愛おしく思いたい、レオノールに無垢なスピリットを込めました
PD映画を観た人にどんなことを考えてほしいですか?
ME大きなことでも小さなことでも、人生について考えてほしいんです。思い描くきっかけになるようなことがあれば、それで十分です。そして、衝動をやることが重要、心にしたがってください、夢を叶えることに繋がっていくと思います。
奇想天外なアイディアの発想法は、混沌のなかランダムにかき集めます。夢、白昼夢、想像したり、繋がりを見つけようとします。かたつむり、落ちてくるレオノール、コピーする幽霊、TVを頭にぶつける・・・私は脚本家より、撮影、カメラマンタイプです。イメージから入ります。
好きな映画監督は、チャーリー・カウフマン、ミシェル・ゴンドリー、スパイク・ジョーンズ。日本では是枝裕和、とくに『空気人形』。 濱口監督作では『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』も見ました。
次回作「Daughters of the Sea」は、本作よりヘンです。3つのストーリー。1つは少女が、海で行方不明になった父が突然現れたという噂を聞き父を探す、2つめは、ペットショップオーナーがフィッシュマーケットで人魚を見つけて生かそうとする、3つ目は、ドキュメンタリー監督がスペインで取材する地図製作者が生き別れた父だったと知る、3つが繋がりがあります、地図のように。